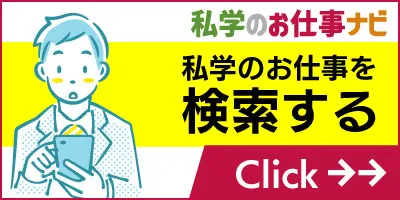さっくりわかる教育トレンド「マインドセット」
以前、教育トレンドで「学習観」についてご説明しました。今回は、「学習観」とも深く関連する「マインドセット」について解説したいと思います。
マインドセットとは?
突然ですが、能力あるいは学習成果について二つの捉え方を示してみたいと思います。
①能力は努力次第で伸ばすことができる。最善を尽くす努力をすることに意味がある。
②能力は変化しない。学力が高い人は能力が高いということである。
このような学習に関する「気持ちの持ち方」が「マインドセット」です。上記は典型的な二例を示しています。①は「成長マインドセット」と呼ばれ、 ②は「固定マインドセット」と呼ばれます。この概念は、キャロル・S・ドゥエックによって提唱されました。
直感的にも共感いただけるかと思いますが、前者のマインドセットを持っていることが学習面においても良い結果に繋がりやすいとされます。もちろん、教育に携わる者であれば、子どもたちにこのようなマインドセットをもってもらいたいと考えるのが自然です。しかし、個々人の内面に位置するものであるため、実際にその形成や変革を意図的に行うことは容易ではありません。
「随伴性」について
ここで、生徒に成長マインドセットを育むために欠かせない「随伴性の認知」という概念を導入します。これは、物事の結果である成功や失敗は、自分の行動と繋がっている(=随伴している)と認知することです。つまり、努力によって目標を達することができるという考え方の土台であり、成長マインドセットを獲得するために大きな役割を果たします。
ただし、「学習性無力感」と呼ばれる、負の「随伴性の認知」も存在します。努力しても結果が変わらないという経験の積み重ねにより形成され、努力自体を諦める原因となります。皆さま自身も、何度トライしても上手くいかず、挫折を経験されたことがあるかもしれません。それ自体は誰しも経験するものですが、過度に反復されると固定マインドセットに繋がる危険性があります。
既にお気づきかもしれませんが、両者ともに努力と起点とした経験という点では類似しています。では、どうすれば「学習性無力感」に陥ることなく、健全な「随伴性の認知」を形成できるのでしょうか。ポイントを押さえるために、また別の概念を導入したいと思います。
結果期待と効力期待
続いて登場するのが、「結果期待」と「効力期待」という概念です。まずは両者を比較したいと思います。
結果期待:自分がある行動をすることで、良い結果に結びつくという見込みを持てること。
効力期待:自分は良い結果に結びつくだろう行動をとることができるということへの見込を持てること。
これはバンデューラの提唱する概念です。前者の結果期待は比較的明快かと思います。「随伴性の認知」に類似した性質のものとすぐにご理解いただけるのではないでしょうか。
後者の効力期待は、定義だけでは少々難解なので例を示したいと思います。例えば「次の定期考査では、数学で80点以上という目標を達成したい。そのために、毎日3時間の勉強を継続すれば目標は実現するだろう」と考えたとします。この場合、
結果期待:毎日3時間勉強することで、数学の目標点数を超えられる
効力期待:数学の目標点数突破に必要な、毎日3時間という勉強を自分は実行できる
となります。いくら「毎日3時間勉強すれば80点以上取れる!」という結果期待が強くても、「自分は毎日3時間勉強できる!」という効力期待が伴わなければ、行動を起こすことは困難です。
だからこそ、「これであれば自分にも努力できそうだ」と子どもたちに感じさせていくことが重要です。これは『学習観』でも登場した、学習方略の提示ということにつながっていきます。
努力を結果に結びつけていくためには、良質な努力が伴わなければなりません。「結果期待」のみならず「効力期待」についても考慮に入れ、努力⇒結果という経験を積み重ねて健全な「随伴性の認知」を獲得させることが成長マインドセットの形成には求められます。
学校現場に落とし込むと、生徒の主体的な学習を促進していくためには、効果が期待でき、かつ生徒にとって過重な負担にはならない方略を教示していくということが、先生方による介入には求められているということになります。
まとめ
「マインドセット」と、隣接する概念について解説しました。
教師の役割は、単に知識を教えるだけでなく、生徒が効果的な学習方法を身につけ、自ら学び、成長していくための支援を行うことです。特に中高一貫校では、6年間という期間を活かし、先取り学習や高度な問題演習に偏るのではなく、生徒が自立した学習者となるための効果的な学習方略を教示し、効力期待を高めることが、これからの教育において重要な視点となります。
(作成:お仕事ジャーナル編集部W)