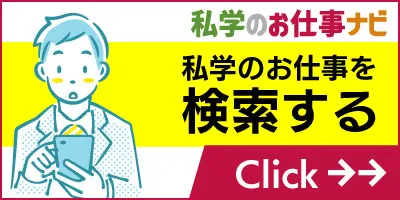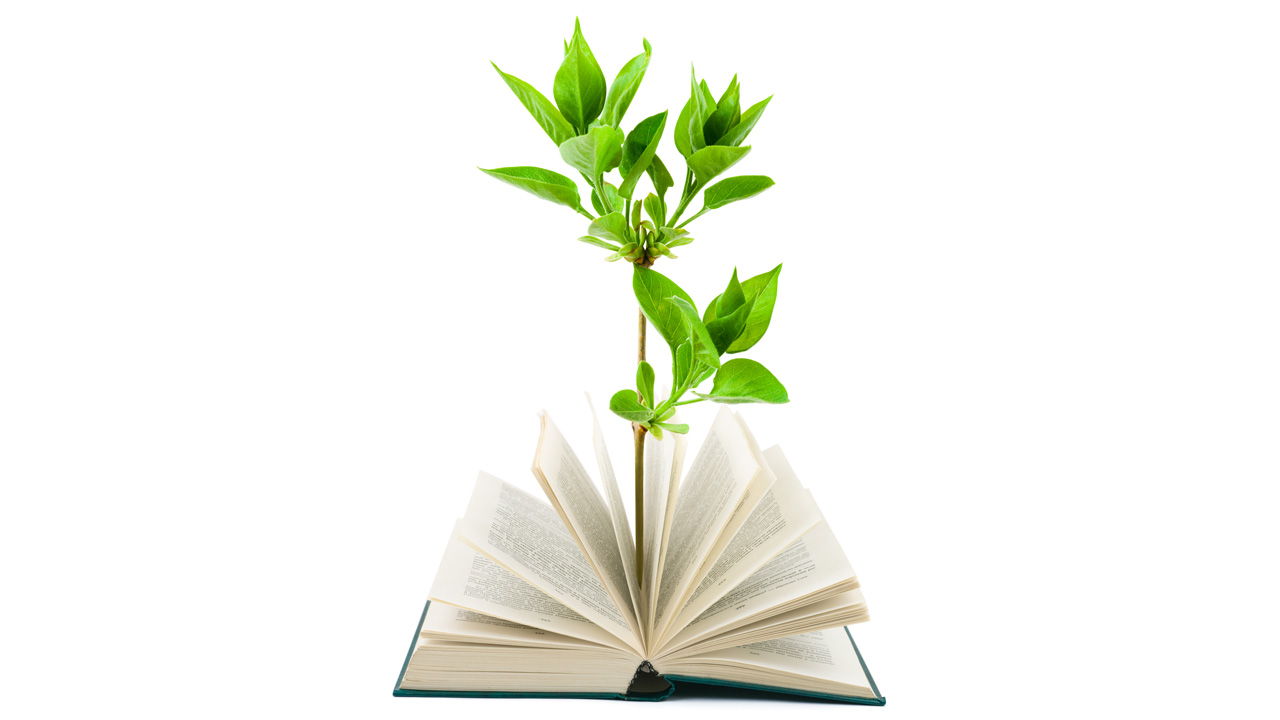私学のユニーク先生インタビュー「追手門学院大手前中・高等学校 福島哲也先生」
今回は追手門学院大手前中・高等学校に、高校教頭である福島哲也先生をお訪ねし、現在のお仕事の面白さや大切にしていること、ご自身の学びや私学の魅力についてお話をうかがいました。
理念を掘り下げ、教員全員でつくり上げた「学校コンピテンシー」
――貴校の特徴について教えてください。
福島教頭 追手門学院大手前中・高等学校は男女共学の中高一貫校です。「独立自彊・社会有為」という理念を掲げ、自主的自立的な精神と確かな個性を持ち、他者や社会に貢献できる人材育成をしています。
――具体的な取り組みを教えてください。
福島教頭 教育理念である「独立自彊・社会有為」の人材育成を行うために、教員みんなでつくり上げた「学校コンピテンシー」があります。これを元に当校として「身につけさせたい力とは何か」を追求しました。自分らしい人生を送れるように、「うちの生徒は何ができて、何ができないか」「教員は何を大切にしているか」を全員で徹底的に話し合いました。
「学校コンピテンシー」では、変化の激しい時代を生き抜くために、探究力を核として制定しました。「For me」「For you」「For us」という3つの次元に分けています。「For me」は自分のために、「For you」は他者のために、「For us」は社会のために、それぞれに必要な力を定め、授業や部活、行事、学校でおこなうすべての活動の中で育んでいます。
自分のワクワクセンサーに反応したことを、探究する
──「学校コンピテンシー」の核となる、探究力への取り組みについて教えてください。
福島教頭 日々の授業も大切にしていますが、もう一つの大きな柱としているのが「探究」の授業です。「何に興味を持っているか」という自分自身を知り、社会を知ることで、自分のワクワクセンサーが何に反応するのかを見つけていきます。
中1から高2までの5年間、系統立てたカリキュラムを作成し、教員は中高関係なく授業を行います。最後は成果物を使ってコンテストや研究会にエントリーしたり、総合選抜で志望校に合格する生徒もいます。探究に力を入れた「グローバルアカデミー(GA)」「グローバルサイエンス(GS)」というコースもあり、「探究」の授業をしたくて、当校を志望した教員もいるんですよ。
 段階的かつ効果的に伸ばしていくために、学校全体でコンピテンシー・ベースの教育に取り組んでいる。
段階的かつ効果的に伸ばしていくために、学校全体でコンピテンシー・ベースの教育に取り組んでいる。
大切にしたい思いや目標が詰まった「学校コンピテンシー」は全教室に貼られ、生徒たちも共有されている。
──「探究」は評価が難しいと言われていますが。
福島教頭 ルーブリック評価やフィードバック評価をはじめ「Ai GROW」を使って探究の評価をしています。また、多くの評価軸を用いて思考力、判断力の評価を明確化することにも力を入れています。自分の強みを知ることで、意思決定の場面で選択肢を増やしてほしいからです。
今何をすべきか、生徒が自主的に選択できる教育環境
──今、学校ではどのようなお仕事を担当されていますか。
福島教頭 公立中学校の教諭時代に、追手門学院の教育長と出会う機会がありました。僕は『学び合い』による数学の授業を進めてきましたが、これは当校の理念と非常に親和性が高いと感じて入職しました。1年目は担任、2年目から主幹教諭という立場になり、昨年から高校の教頭職に就いています。
──先生が実践されてきた『学び合い』の授業について教えて下さい。
福島教頭 大学卒業後、東大阪市の公立中学校で数学を教えながら、さまざまな教育手法を実践していました。授業の工夫を重ねるうち、上越教育大の西川純先生が提唱された『学び合い』に出会います。これは私が教員になってから腹落ちする授業実践だったんです。
──授業はどのように進められるのですか?
福島教頭 『学び合い』は、一人も見捨てないことをポリシーとした授業実践です。そのためには、一斉に同じ指示を同時に行う授業では実現できません。生徒たち自身に行動を選択できる環境を与えなければいけません。授業で伝えたいことをまとめた動画や演習問題を前日までに配信し、当日は学校でしかできないことを選択できる環境で授業を行っていました。生徒が自らの課題を自分たちで解決法を調べ、考え、教え合ったりする。僕は生徒からの質問を受けたり、ヒントを出したりするだけ。従来のように教科書に書かれた授業のポイントを読み上げたり、板書したりはしません。
生徒たちは教室を自由に動き、好きな席に座って課題に取り組みます。大切なのは「自分で選択をさせる」ということ。「今、何が必要なのか」を自分で考え、選択肢の中から選び取っていく時間を与えるということ。
──準備したら、後は生徒に任せて見守ると。
福島教頭 教育系youtuberのコンテンツや、以前の授業の動画を見る生徒もいますが、それもいいんです。自分が「ここでつまづいた」「この公式をきちんと理解したい」という自己評価ができているわけですから。
一人ひとりがどこを学習しているのか理解するために、単元テストというターニングポインだけは決めておきます。そこに向かって遅れを感じれば走る必要があるし、先を行っているのなら余裕を持って進めればいい。とにかく「生徒が自主的に選択して学ぶ」ことが重要なんです。
クラスの仲間をひとりも見捨てず、課題の全員達成をみんなで目指す
──『学び合い』でもっとも大切にしていることは?
福島教頭 一人も見捨てないことです。各自の目標をみんなで達成できるようになることですね。それぞれの目標値と現在地を見比べた「差分」をあと何日で埋めるのか。全員が個人の目標を達成するために必要なことをする。
また自由に進めるだけでなく、そこをつなぐマインドが不可欠です。「自分さえ良ければいい」ではなく、自分は社会の一員であることをみんなで認識しあうことを、僕は数学の授業で伝えたいと思っていました。
──生徒の成長に関してどのように感じますか?
福島教頭 「教師が教えないと理解できない」と言われることもありますが、そんなことはないと思っています。まずは、自分で考える力は確実に伸びますよ。同時に、仲間のことを互いにおもんぱかることができる集団づくりにも大きな教育効果があると感じています。
『学び合い』の授業では、日々ドラマが起きます。普段は大人しい数学の得意な生徒が数学の授業ではヒーローとなることがあったり、使命感を持って熱心に友だちに説明する場面や、普段は関わらない生徒たちがグループとなって問題を解くのに熱中する姿も見られます。
教員は天職、子ども一緒に夢中になって心動される瞬間がある
──キャリアを振り返って、やりがいを感じるのはどういう場面でしょうか?
福島教頭 公立で14年、当校で7年と教員生活は21年目を迎えましたが、教員は僕にとって天職だと思っています。やりがいを感じるのは、やはり生徒の成長や変化を感じたときです。あと教員が新しいチャンネルを手に入れ、フェーズが上がっていくのを目の当たりにするのも嬉しい。層の厚い職員室になるほど、その学校は魅力を増しますから。
──1日のスケジュールを教えて下さい。
福島教頭 午前中は会議中心で、職員室にいる時は教員と対話することが多いですね。放課後は生徒の面談もします。当校の「追手門モジュール」では、1日の終りに振り返りや教師との面談があって。日に1回は校内をまわって生徒の様子を見たり、宿泊行事の引率といった形で生徒と接点を持っているからか、僕にも面談を依頼してくれる生徒がいることは嬉しいです。
 「探究力」養成を目的とした「追手門モジュール」では1日の終りに振り返りを通して自らと向き合い、
「探究力」養成を目的とした「追手門モジュール」では1日の終りに振り返りを通して自らと向き合い、
さらに教師との個別面談によって前に進むためのサポートを受ける。
──他業種から転職される方はいらっしゃいますか?
福島教頭 4月から赴任する方は教育とは畑違いの業種からの転職組の方もおられますし、社会人経験を持つ方も歓迎しています。それと僕自身もですが、当校は公立の学校で教えていた教員も多いんです。
──貴校が求める教員の人物像を教えてください。
福島教頭 これは僕の意見ですが、まず子どもと関わることが好きであること。そして生徒と一緒に夢中になれること。子どもたちに向けて、自分自身がどんな人生を歩んでいきたいのか、なぜ教師という仕事を選択したのかを、「自分の言葉」で語れる人がいいですね。
──教員を目指す人にメッセージをお願いします。
福島教頭 当校で教員をすると「心が動く」、そうした経験がたくさんできると思います。