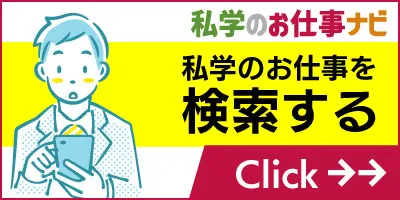校務の中で「自己研鑽」の機会! ~学校研究と研修について~
学校教職員には校務の中で、教育活動に必要な知識を得て、その質をより良く高めることのできる機会があります。
それが、学校研究や研修です。これらは、貴重な自己研鑽の機会となります。
今回は、学校研究や研修について、見ていこうと思います。
<学校研究>
学校研究とは、教育の質を向上させたり、教育の特色をより生かせるようにしたりするために、教職員が一丸となり、教育について研究を行う機会のことです。校内研と呼ばれることもあります。
以下のような学校研究が行われています。
授業研究
授業における、より良い指導法を模索する試みです。
特徴的な教授法や指導システムを試し、その効果検証を行います。
学級学年運営研究
児童生徒指導に焦点を当てた研究です。
それぞれの児童生徒の実態に合わせて、どのような指導が効果的なのかを検証します。
学校教育研究
学校全体のカリキュラム、システムの効果を評価し、より良い方法を模索します。
学習環境研究
教室環境や設備・施設環境、学習資料の効果を検討し、改善を図ります。
教職員支援研究
教員の教育技術や指導方法の向上を目指し、研修方法や働き方、あり方などについて模索します。
他にも、特別支援教育研究やグローバル教育研究など学校の特徴を生かした研究が行われています。
加えて、私学の場合は、それぞれの学校の色を生かした独自の研究が行われていることがあります。例えば、国際バカロレア(IB)プログラムを導入している学校では、よりグローバルシチズンシップの高まりが期待できる指導体制や海外研修のありかたについて模索しています。
この中で、最も多いのが、授業研究です。例えば、国語の時間にグループディスカッションや実践的な問題解決活動を取り入れて児童生徒の主体的な学習意欲を醸成する研究、数学の授業において映像資料を先に視聴させてから授業を行う反転学習の研究などがあります。
大切なことは、これらの取り組みを行うことではなく、理想とする子どもたちの姿がどのようなものであるかの統一見解を共有し、そこに向かって仮説、検証、振り返りのサイクルを有機的に回していくことです。
<研修>
研修とは、教職員の業務をよりよく行うための知識や技能の習得を学ぶことができる機会です。講演やセミナー形式で行われることもあり、自校だけでなく他校や教育委員会、私学連合などで開催されることもあります。
以下のような研修が行われています。
年次研修
例えば1年目の新任教員は、初年度に専門の指導者がつき、授業の進め方やクラス運営の方法について個別指導を受けます。また、同期の新任教員と共に研修会を通じて情報交換やスキルアップを図ります。2年目や5年目、10年目など、それぞれの経験年数に応じて求められている能力について高める研修機会が持たれます。
専門領域研修
それぞれの専門の教科や分野について、教授法や評価方法、授業での実践例について学びます。他校や外部の研究機関と連携して行われることも多く、新たな手法に触れる機会となります。
ICT研修
デジタル技術の進展に伴い、教職員向けにICTを活用するための研修が行われます。例えば、オンライン授業の運営方法やデジタル教材の作成、データ活用、校務システムの運用方法などを学びます。
メンタルヘルス研修
教職員の心の健康をサポートするための研修も重要です。ストレスマネジメントやセルフケアの方法、同僚や生徒、保護者との関係性を良好に保つための心理的アプローチを学びます。
他にも、役職別研修やリフレッシュ研修など多様な学びの機会があります。
加えて、私学においては、学校の特色にあった専門家を招聘しての講演や、海外の拠点を生かしての研修が行われる場合もあります。統一的な研修プログラムが組まれている公立学校に比べて、予算や方法が柔軟なのが私学の研修体制の特徴です。
このような研修では、他校の実践に触れたり、他校の教職員や外部の人と交流したりすることも多いです。自校での「当たり前」を、他校実践や客観的な見解に触れることで見直す機会になるかもしれません。
日常の業務の多忙さゆえに、このような機会をおざなりにしてしまうことがありますが、「常に学び続ける」「どんなことからも成長の種を見つける」ことは、不確かな時代を生きる子どもたちの良きお手本となるのではないでしょうか。
このように、学校研究や研修などの自己研鑽の機会に着目し、自身のキャリアビジョンを描いてみるのも面白いかもしれません。
(作成:お仕事ジャーナル編集部A)